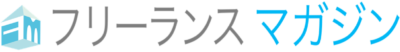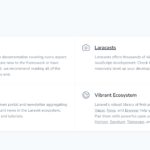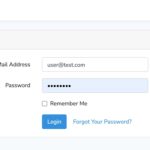てくてくフリーランス優美(第24話)

ピンクのワンピースと、黒いスカートと、あとジャケットに、サテン系の生地のシャツと。
あれこれ服をテーブルやソファに広げて、私は悩みに悩んでいた。
玉口君と気持ちをぶつけあったあの電話から一ヶ月、毎日電話しあう様になって。私と彼は、なんだかんだでのんびりと付き合いを続けていた。
そして明日は、彼と、初めて一緒に遊びに行くことになった。
「デート……ってことでいいよね!?」
鏡の中の私に問いかける。顔面は『お休み前のレスキューマスク』とかいうやつにおおわれているから、ちょっとしたホラーだ。
仕事でちょっと無茶をしてきたツケか、普段から肌も髪もお手入れが足りてないからか、ギリギリ間に合わせた感がすごい。
「でも、デートしようなんて口で言わないのが普通だよね……」
今までの彼とだって『今度の日曜日に遊ばない?』とか、一緒に過ごすのを繰り返して、やがて『付き合おうか』って確かめるような雰囲気だった。デートも似たような感じ。
「デートだよねって確かめたくなるの、初めてかも」
そんなドキドキとした気持ちで迎えた翌日。
喫茶店の中、私と玉口君は向かい合って座っている。
気温はちょうど良くて、手のひらの中にあるコーヒーは熱々だ。
「……話したいことがあるって、何?」
デートの待ち合わせ先の喫茶店で、何故か玉口君は意味深に『遊びに行く前に話したいことがある』と、言い出したのだった。
「実は、ですね」
重々しく言う玉口君に、私の喉もごくりと音を立てる。
お互いに気持ちをぶつけあった私たちは、お付き合いから始めている。でも二人とも何かと仕事中心に生活していたのもあって、今までの関係の延長線上にいるような感じがしていた。
服も悩んだけど、結局、いつも通りのシンプルなワンピースだ。
(も、もっと可愛い服とか着てくればよかったかなぁ……)
デートっぽい雰囲気にしていたら、こんな重い空気にならなかったかな。
そう悩んでいると、玉口君がそっと、何かのカギを取り出した。何となく、私も見覚えのあるカギだ。
何とそのカギは、カバンの中にある私の自宅の玄関のカギに、そっくりだった。
玉口君がそのカギを出してきた意味が分からなくてじっと見つめていると、彼が急に頭を下げた。
「すみません。俺、実は、優美さんと同じマンションに住んでいるんです」
「……ええっ!?」
「いつかは絶対言わなきゃ、と思ってて、いろいろタイミングのがしてて、今日しかないって思って……」
予想の斜め上を行く言葉に、私は目を点にする。
「え、それって」
「たまたまだったんです。一番今の会社に近くて、自宅を仕事場にしても問題ない、賃貸のマンションってそこしかなくて。単身向けの部屋だったから、ラッキーって思ってたら」
「私が、住んでるマンションだった?」
「はい。実は、前に先輩をマンションまで送って行った時に分かってたんですけど……」
「もしかして、家飲みしようって言ったきりになっていたのも」
「言い出せなくて……」
混乱したまま、私はぽつりと呟く。
「つまり、マンション規模で見れば……同棲?」
私と玉口君の間に、沈黙が広がった。
顔が真っ赤になるのを感じて、私は首を勢いよく横に振る。
「ごめん! 忘れて!!」
「忘れようがないです、優美さん」
「もーっ!」
でもこれで、家飲みをする決心がついたみたい。
その日のうちに私は玉口君の家におじゃまして、同じマンションだから『すぐに帰れるから』と言って、一緒に朝まで飲み明かしてしまったのだった。